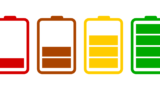日本の電力の姿
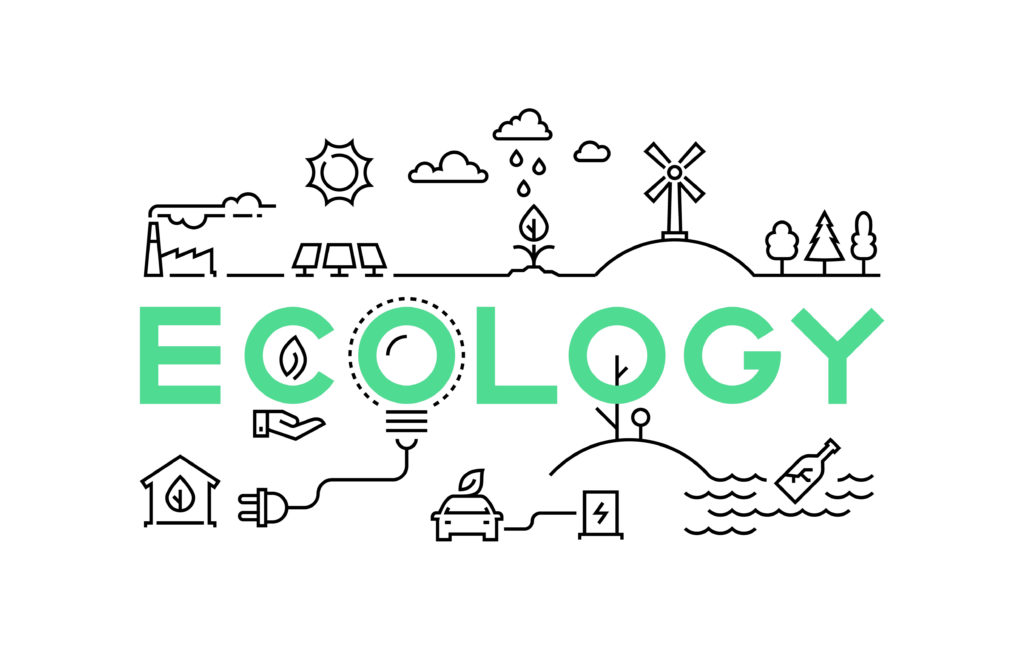
この地球には多用な資源があります。こうした資源を熱と電気という二次エネルギーに変換し、私たちは利用しています。
ここでは電気に注目し、「どうやって資源から電気を生み出すのか(発電)」「生み出した電気をどうやって送り届けるのか(送配電と蓄電)」「自然エネルギーをたくさん用いられるように大変革が進む電力システム改革について」等々、日本の電力にまつわることをまとめていきます。
多様なエネルギーの源
エネルギーの収支、化石燃料の代替手段
現在の私たちが使用するエネルギーはどんな種類でどのくらいの量がどんな用途で使われているのでしょうか。大部分を支える化石燃料からの脱却に向けてどんなオプションが考えられるのか、まとめました。
原子力
原発事故以降火力に主役の座を明け渡した原子力エネルギーですが、脱炭素電源というメリットが再び注目されています。安全面や廃棄物処理というデメリットを踏まえ、既存の原子力発電所で将来どの程度の割合を賄っていけるのでしょうか。
福島原発事故はなぜ起きたしまったのでしょうか。事故の最中原子力発電所の中で起こっていたことをわかりやすく徹底解説します。
本稿は原発の賛否を示すものではなく、技術的観点から掘り下げ、わかりやすく福島原発事故について解説することを目的としています。
再生可能エネルギー
脱炭素化の流れの中で化石燃料に変わる主力電源として再生可能エネルギーが急増しています。その大本命である太陽光は今後どのくらいのびていくのでしょうか。そのポテンシャルを掘り下げます。
安定で安価な再生可能エネルギーという圧倒的メリットを持つ水力発電ですが、様々なデメリットも併せ持っています。適地が限られる中で、日本の水力発電の展望についてまとめます。
火山帯に位置し、世界で第三位の地熱資源を有する日本ですが、その発電量は1%にも満たないのが実情です。そんな地熱発電のメリットとデメリット、今後の展望をまとめます。
バイオマス発電は使用する燃料が多様で何を使うかによって、経済性・補助金の額・二酸化炭素排出量などが大きく変わってきます。
魅力的な燃料は調達が難しい中、地産地消なバイオマス発電発展の鍵は、林業自体の発展です。そんなバイオマス発電についてまとめます。
エネルギーを送る、貯める
送電網・配電網・連携線・電力とガス
日本全国どこでも電気を使うことができるのは、発電所が豊富にあるだけでなく、その総配電網の存在が欠かせません。再エネが主体となっていく中で、そのあり方も大きく変化していきます。送電線が一体どんな仕組みで形成されているのか、また再生可能エネルギーの普及が進む欧州はどんな電力ネットワークとなっているのかまとめました。
少数の大規模安定電源から、多数の分散型再生可能エネルギー電源への転換、これを実現していくためには、送電線の運用ルールを変えていく必要があります。単に増強するのではなく既存の送電線を有効活用するための仕組み「ノンファーム型接続」について背景からまとめます。
カーボンニュートラルへ向かう中では二酸化炭素を排出するガスは逆風ですがどういった方向性に向かうのでしょうか。電力との比較、都市ガスとプロパンガスの違いなどに触れつつ、切り札のメタネーションとは何かについて迫っていきます。
蓄電池
不安定な再生可能エネルギーの普及とEVの普及により注目を集める「蓄電池」様々な蓄電池種類をご紹介します。その中でも昨今メインとなってきているリチウムイオン電池が注目される理由に迫ります。
家庭のエネルギーのあり方
これまでの大規模発電所における化石燃料を主体とした発電から、再生可能エネルギーを主体とした分散電源による発電への転換が進んでいます。
様々な発電方法に対して、エネルギー密度比較を行います。その中でも現在一般家庭で普及している太陽光発電に商店を当て、太陽光発電で一般家庭のエネルギーを全て賄うことは可能なのか、検証します。
太陽光発電による発電量は年間でどれくらいでしょうか。一般家庭でのエネルギー消費量と比べ、それぞれの季節変動に注目しながら、太陽光だけで生活するにはどうしら良いか深堀りします。
電力自由化に向けた電力システム改革
発電・送電・小売事業者、電力システム改革の全体像
電力自由化に向け、20年4月の発送電分離を持って区切りを迎えた電力システム改革の全体像についておさらいします。
電力事業の変遷や発電・送電・小売を担う事業者についてもまとめます。
電力システム改革を推進、検証している経産省のエネ庁以下の審議会ですが、大量の委員会とワーキンググループがあり複雑です。これを一度俯瞰して見れるようにまとめてみました。
電力市場について(卸電力市場・非化石取引市場・容量市場)
日本の電力市場の全体像について。
まずは、市場規模や複数に分かれる市場の構成についてまとめています。
二酸化炭素を出さない電源(非化石電源)の割合を増やしていこうという動きが加速しています。法的な拘束や実際に非化石電源を取引するための非化石証書とは何でしょうか?脱炭素化に向けた重要な役割を果たす仕組みをまとめます。
そもそも日本で必要な電源を確保するためにはどうしたら良いのか、そのインセンティブを与える「容量市場」について。